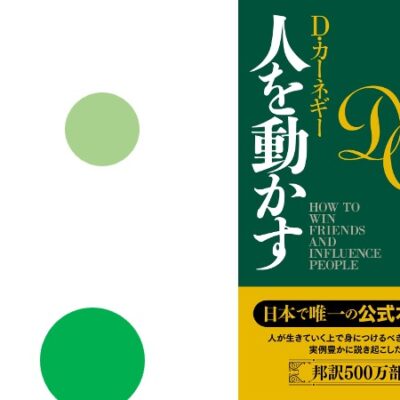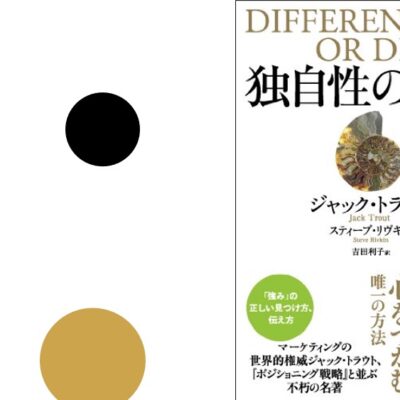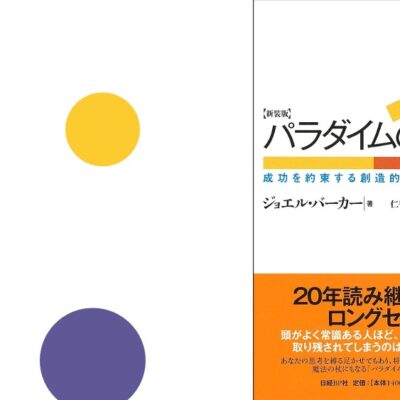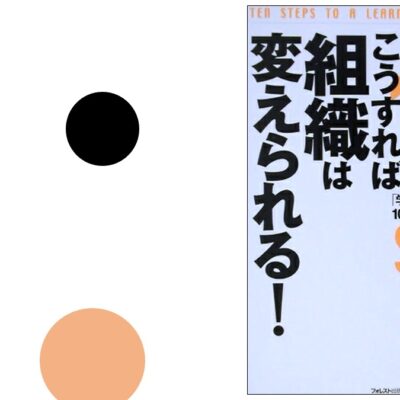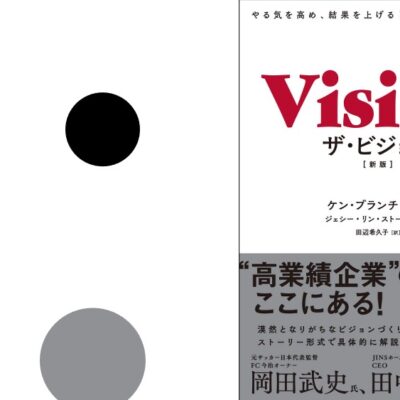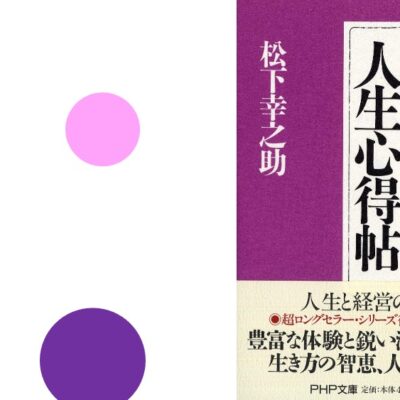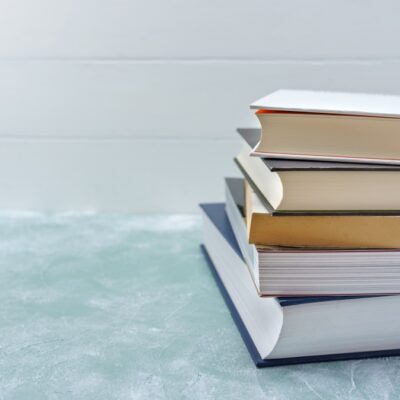エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化する 私の読書メモを紹介します。
著者:グレッグ・マキューン
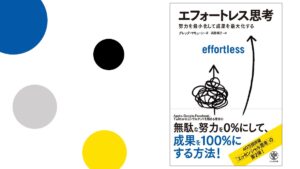
目次
• 1.本書からピックアップ
• 2.感想
• 3.この言葉の活かし方
• 4.まとめ
• 5.私の読書メモで紹介した本
1.本書からピックアップ
不運な出来事が起こった時、それをあきらめて受け流すのは難しい。どうしても不満や怒りが湧いてくる。他人の愚痴を見るうちに、心が少しずつむしばまれ、世の中の悪いところばかりが目に付くようになる。そして不満に身を任せているうちに、頭の中に無価値なゴミが溜まり、自由に使えるスペースがどんどん減っていく。足りないものに目を向けると、足りないことばかりが増えていく。逆に、すでにあるものに目を向ければ、心はどんどん満ち足りてゆく。
みんながやっていることをとても上手にやることよりも、誰もがやっていないことをそこそこうまくやったほうがいい。さらに、誰もやっていないことをとことん極めれば、あなたの価値は飛躍的に高まる。知識の累積的な成果を得るために、まずやるべきことは他の人から学ぶことだ。だが、最終的な目標は、自分だけの知識を見つけ出し、伸ばしていくことである。
いつも枝葉を切っていれば、枝葉を切るのは上手くなるかもしれない。だが、それでは問題は解決しない。この先いつまでたっても、同じ問題に悩ませる悩まされることになる。あなたの人生や仕事において、繰り返し起こる問題やフラストレーションはないだろうか。単に枝葉を切るのではなく、根本からやっつける方法を考えてみよう。
2. 感想
「足りないもの」に目を奪われると、人生は“複雑”になる
- 本書は、「足りないこと」に目を向けるか、「すでにあること」に意識を向けるかで、私たちの思考の質と感情の在り方が大きく変わるという指摘をしています。不満・怒り・愚痴といった“内なる雑音”は、知らぬ間に思考スペースを侵食し、創造性や前向きな選択を奪います。この状態を放置しておくと、ビジネスにおいても個人の生活においても、「がんばっているのに成果が出ない」「何をしても報われない」と感じる状態を生み出します。
- しかし著者は、視点をほんの少し切り替えるだけで、努力が報われる感覚=エフォートレスな状態”を取り戻せると言います。これは、「本当に大切なことに集中し、それ以外のノイズを静める」という“思考と行動の最適化”に関するメッセージです。
「誰もやっていないこと」を“そこそこ”でいいから始める
- さらに著者は、「誰もやっていないことをそこそこやること」の価値についても触れています。現代は「うまくやること」「効率的にこなすこと」が重要視される風潮がありますが、本書では“人と同じ競争の土俵で勝つ”よりも、“自分の土俵をつくる”ことの方がはるかに価値があると説いています。ここには、「完全主義を手放す」「比較から解放される」といった、現代人の多くが抱える“努力疲れ”を解放するヒントが詰まっています。
- また、知識やスキルも、最初は「借り物」でも構わない。学びを続けることで、やがてそれは「自分だけの知」となり、人から頼られる存在や、独自の貢献ができる個人へと進化していくという考え方に勇気が得られます。
「枝葉を切る」だけでは、人生は軽くならない
- 何度も繰り返されるフラストレーション。「あれ、また同じことで悩んでるな…」と気づいたとき、私たちはつい、問題の表層だけを処理して、次のトラブルを“やり過ごす”ことに慣れてしまいます。しかし著者は、「それではいつまでも根っこは変わらない」と警告します。
- ここで語られるのは、「表面的な改善」ではなく「構造の見直し」に目を向けること。つまり、努力するのではなく、“仕組みそのもの”を変えることで、もっと楽に結果が出せる道があるという視点です。これは、ビジネスにおける業務改善や戦略の見直し、人生における習慣形成など、あらゆる分野に通用する“根本を見極める思考習慣”の大切さを教えてくれます。
3. この言葉の活かし方
思考の「空白」を守る時間を日常に組み込む
具体的な活かし方
• 仕事の前に、今日やらなくていいことをリストアップして“手放す”時間を持つ
• 日報や週報に「今日感謝できたこと」を一行書く習慣をつける
実践例
チームミーティングの冒頭に「今週、うまくいったこと」を1人ひと言ずつ共有する時間をつくることで、「足りないこと」ではなく「すでにある価値」に意識を向ける集団思考を育てる。
誰もやっていないことを“自分なりのやり方”で始めてみる
具体的な活かし方
• 周囲と比較せず、自分のペースで「得意になれること」を見つける習慣を育てる
• 自分の知識や経験をノートやブログに整理し、“自分の知識資産”として蓄積する
実践例
専門分野での小さな解説記事を毎週1本書いて公開することで、「誰もやっていないテーマ」における存在感が徐々に高まる。結果的に、情報発信が“自分だけの価値の可視化”につながっていく。
繰り返す問題を、構造レベルで“やっつける”発想を持つ
具体的な活かし方
• チームで「またこの問題か」と感じたとき、原因の仮説を出し合い“習慣”や“ルール”の見直しを行う
• 日常の小さな不便も、「仕方ない」ではなく、「仕組みを変えるチャンス」として捉える
実践例
営業で見積もりミスが繰り返されるなら、個人の注意力を責めるのではなく、見積フローのテンプレート・チェックリスト・確認工程をチームで再構築する。“努力の上塗り”ではなく、“仕組みの再設計”でミスを減らす。
4.まとめ
『エフォートレス思考』で、著者は、「もっと頑張る」のではなく、「もっと楽に成果が出る方法はないか?」という視点への転換を問いかけます。
• みんながやらないことを“ほどほどにやる”ことが、実は差別化の起点になる
• 同じ問題を何度も繰り返すのは、努力不足ではなく“構造の問題”かもしれない
あなたが今、取り組んでいる“頑張り”の中に、「実はもっと楽にできる方法」はないでしょうか?それに気づくためのスペースを、自分自身の中に確保するところから始めてみましょう。その先に、もっとシンプルで、もっと深く結果につながる道がきっと見つかるはずです。
5.「私の読書メモ」でご紹介した本
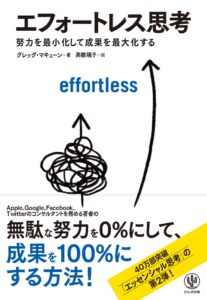
エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化する(Amazon)
日曜の朝が楽しみになる「ビジネスリーダーの書棚」。名著を通じてビジネスの知見を探究する読書会です。変化の激しい時代だからこそ、「賞味期限の短い、誰もが手にする本」ではなく、「時を超える本」を一緒に味わっていきましょう。毎月1回、日曜日に定期開催しています。
カテゴリー
・私の読書メモ
Copyright Ooba Consulting Office All Right Reserved.
本コンテンツをを無断複製することや転載することを禁止します