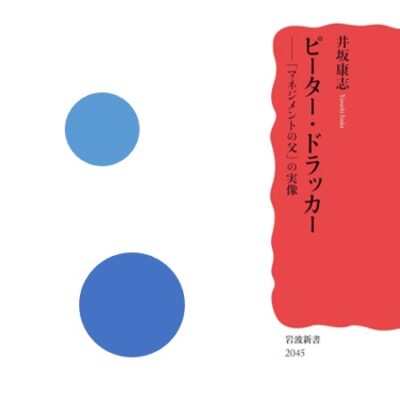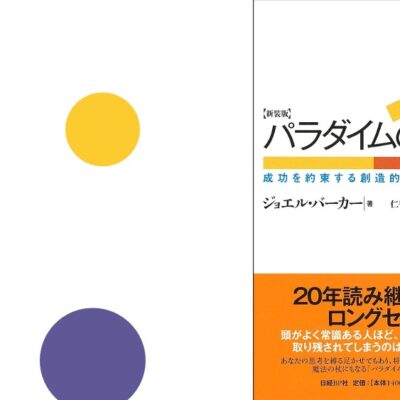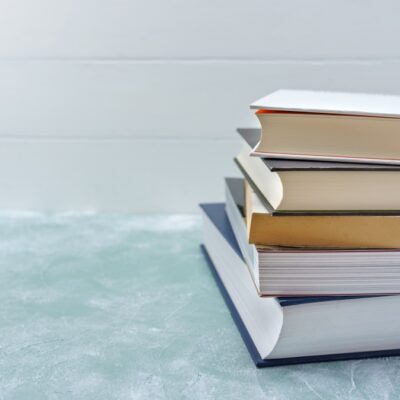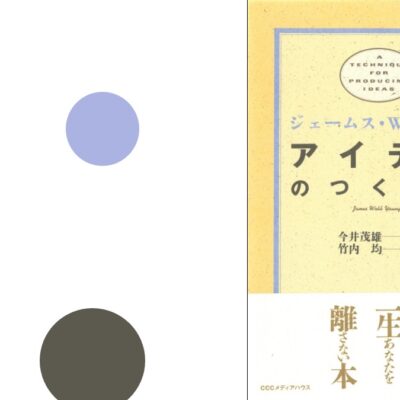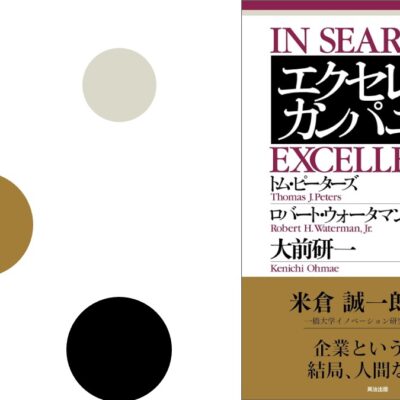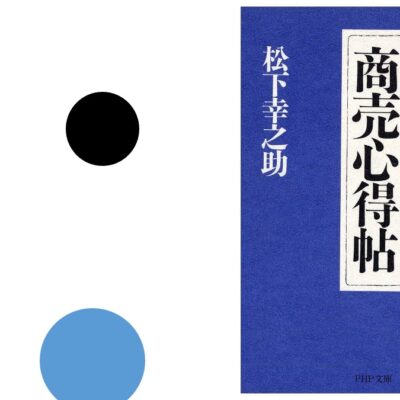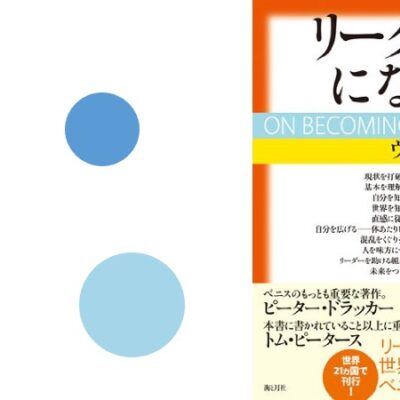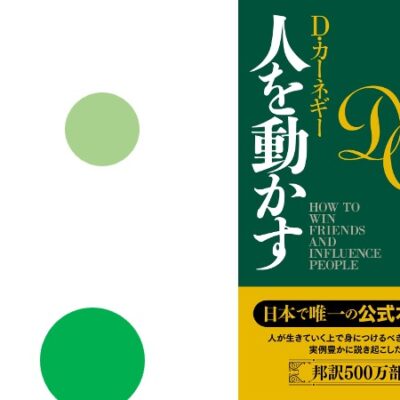稲盛和夫「高収益企業のつくり方」私の読書メモを紹介します。
著者:稲盛和夫
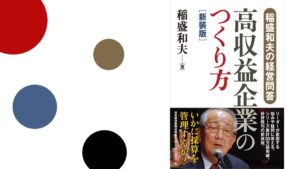
目次
• 1.本書からピックアップ
• 2.感想
• 3.この言葉の活かし方
• 4.まとめ
• 5.私の読書メモで紹介した本
1.本書からピックアップ
経営の目的を明確にした瞬間から、私には何をするにも迷いがなくなり、みんなのためにいかなる苦労もいとわないと言う新たな決意が湧いてくるのを感じました。人間が全身全霊で打ち込むには大義を必要とします。「大義」とは個人の利益ではなく、世のため人のためと言う「公」の利益のことです。
部門ごとの業績によってボーナスを上下すると言うのは、あまりにもドライな方法であり、計画以下の利益しか出ない部門の人間はやる気を失ってしまいます。一時的にボーナスが増えて喜んでる部門も計画以上に利益が出なくなり、ボーナスも増えないとなれば、急に冷めてしまい、意欲がなくなるのです。京セラでは、業績の良い部門にはボーナスで報いるのではなく、その功績を称賛することにしています。精神的な栄誉を与えているのです。
人間の能力は、未来に向かってどんどん伸びていくものだ。今考えてできないことでも、半年先にはできるようになっているはずだ。だから、我々の能力を未来進行形で捉え、必ずできるはずだと信じて、頑張ろうではないか。未知の新技術を開発する際、リーダーは、高い目標を掲げ、自分たちの能力を未来進行形で捉えることが必要です。
2. 感想
経営における「大義」とは、全身全霊で打ち込むための原動力である
- 稲盛和夫氏が説く「大義」とは、単なる理念やビジョンではなく、経営に命を懸ける覚悟を生み出す“心の支柱”です。特に印象的なのは、「経営の目的が明確になった瞬間、迷いが消えた」という言葉。これは、経営者である自分自身が“誰のために、何のために”この事業をやっているのかを明確にすることで、あらゆる判断や行動に一貫性が生まれることを示しています。
- 「大義」とは、世のため人のためという「公」の利益。この視点があるからこそ、困難にも粘り強く立ち向かい、組織全体を同じ方向へ導くことができる。短期的な利益や個人の損得を超えた「目的」を持つことの重要性が、本書を通じて強く伝わってきます。
“称賛”が人を動かす
- 稲盛氏は、部門別業績によってボーナスを上下させる仕組みを「ドライすぎる」とし、京セラではあえて称賛という精神的報酬に重きを置くという運用をしています。
- これは、ハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」にも通じるアプローチだと思いました。ハーズバーグの理論では、「給与」「待遇」「ボーナス」といった報酬は“衛生要因”であり、不満を減らすことはできるが満足を高めることができないとしています。一方で、「承認」「達成感」「成長実感」といった“動機づけ要因”こそが、人のやる気を引き出すというのです。この考えを、稲盛氏は実際のマネジメントで徹底したのだなと思いました。
- 功績を讃え、名誉を与える文化は、成果主義の落とし穴(短期志向)を防ぎ、全体最適の組織運営につながるという点で、極めて実践的です。
“未来進行形の能力観”が、可能性を最大限に引き出す
- 稲盛氏が説くもう一つの核心は、「能力とは未来進行形で考えるべき」という発想です。人は自分の現在の能力を基準にして目標を決めがちですが、氏は「今はできないかもしれないが、半年後にはできるはずだ」と信じて目標を掲げることの大切さを語っています。これは単なる楽観主義ではなく、「人間の可能性」を信じる哲学であり、技術開発や事業成長において“自ら限界を決めない”ための思考法でもあります。挑戦するリーダーの姿勢が、チームにも波及し、「できるかどうか」ではなく「どうやったらできるか」に発想が転換されるのです。
3. この言葉の活かし方
経営や仕事の“目的”に「大義」を取り入れる
具体的な活かし方
• 会社の目標を考える際、「公(社会)」の視点を一文加えてみる
• 経営会議や方針発表で、“この事業の意義”を語る時間をしっかり取る
実践例
採用時に、事業内容よりも「なぜこの仕事が社会に必要なのか」を語ることで、共感に基づいた人材採用やチーム形成が可能になる。
精神的報酬を重視する組織文化をつくる
具体的な活かし方
• 表彰は金銭以外の形でも行う(社内報・称賛カード・全体朝礼など)
• 成果をあげた部門や個人には、感謝と敬意を言葉で贈ることを習慣にする
実践例
「月間最優秀チーム」ではなく、「月間ベストチャレンジ賞」を創設。売上に直結しない活動(新提案、改善アイデア、後輩育成など)についても積極的に称賛し、自発性と挑戦を奨励する空気を育てる。
目標設定の際、「未来進行形」の視点で能力を捉える
具体的な活かし方
• 「できない理由」より「できる前提で考えるには何が必要か?」を問いかける
• 若手社員には、短期のスキル評価ではなく、成長プロセスを踏まえた支援を行う
実践例
「売上○○万円達成」という目標を、「この能力が半年後に身につくと仮定して、その上でどこまでできるか?」という視点で見直す。これにより、自分自身に対する制限をはずし、ストレッチ目標に挑戦する姿勢が醸成される。
4.まとめ
本書は、単なるノウハウ集ではなく、高収益企業の背後にある“目に見えない原理原則”を明らかにしています。稲盛和夫氏の語る言葉一つひとつには、人と組織を本気で動かすための「経営の本質」が込められています。たとえば、「大義を持つこと」「精神的な報酬を重視すること」「能力を未来進行形で捉えること」など、どれも数字だけでは割り切れない“人間の本質”に根差したアプローチです。
こうした視点は、短期的な成果を追うだけの経営では決して辿り着けない、持続的成長の礎となります。
もちろん、稲盛氏といえばアメーバ経営や部門別採算管理など、数字を徹底的に重視する経営者として知られています。しかしその土台には、「なぜ経営をするのか」「誰のために働くのか」といった数値を超えた“哲学”が明確に存在していることを、本書の問いかけから読み取ることができます。
経営とは、人を動かすこと。
そして、人を動かすとは、心を動かすこと。
数字と心、その両輪を回していくことの大切さを、改めて深く実感させてくれる一冊です。今、あなたが経営に迷いや課題を感じているなら、数字の奥にある「本質」に立ち返る時なのかもしれません。
5.「私の読書メモ」でご紹介した本
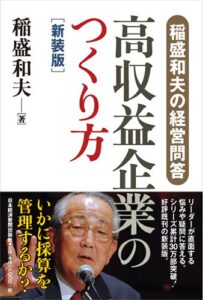
カテゴリー
・私の読書メモ
Copyright Ooba Consulting Office All Right Reserved.
本コンテンツをを無断複製することや転載することを禁止します