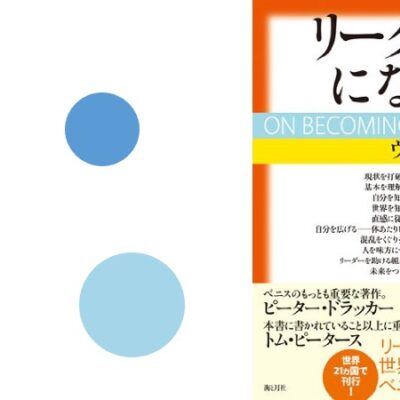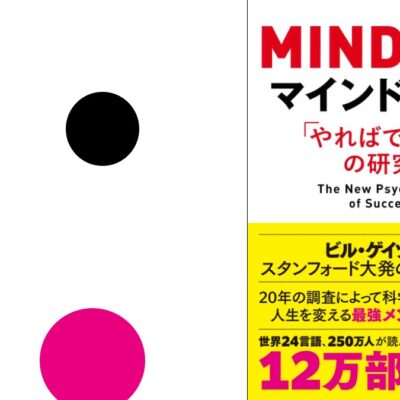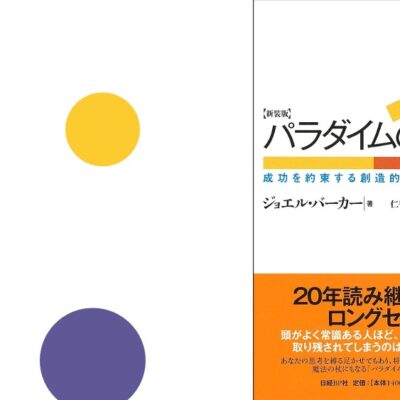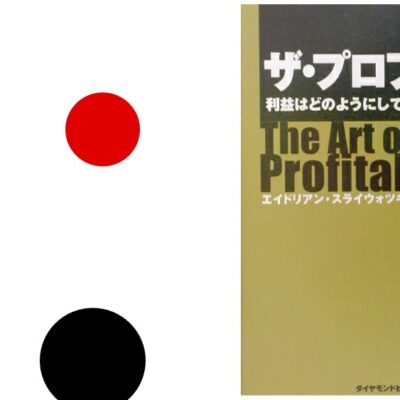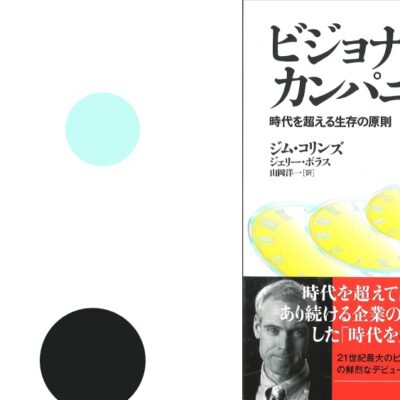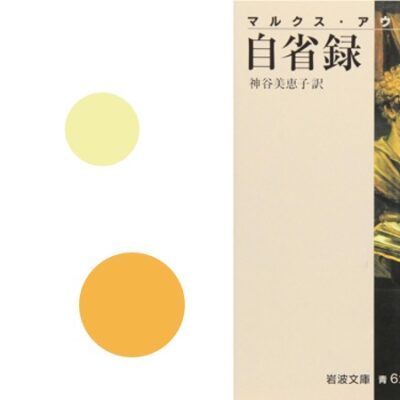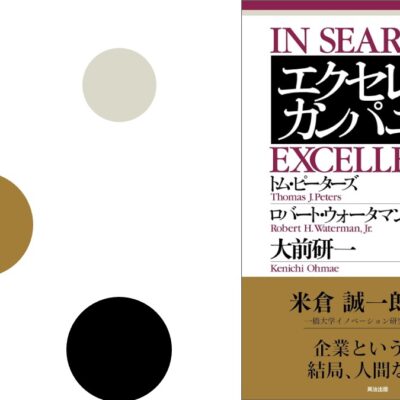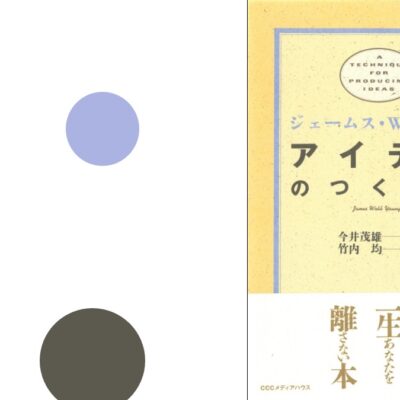ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代 私の読書メモを紹介します。
著者:ダニエル・ピンク 翻訳:大前研一
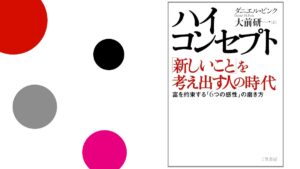
目次
• 1.本書からピックアップ
• 2.感想
• 3.この言葉の活かし方
• 4.まとめ
• 5.私の読書メモで紹介した本
1.本書からピックアップ
これからは創造性があり反復性がないこと、つまりイノベーションとかクリエイティブプロデュースといったキーワードに代表される能力が必要になっていく指摘労働者がやっていた反復性があったり、再現性があったりする。仕事はコンピューターやロボットに吸収される。たとえ反復性はなくてもインドなどにアウトソース外注されてしまう。
この本には、日本人がこれから一番身につけなくてはいけない、右脳を生かした全体的な思考能力と新しいものを発想していく能力、そしてその実現可能性を検証するための左脳の役割などについてわかりやすくまとめられている。
ハイ・コンセプトとは、パターンやチャンスを見いだす能力、芸術的で感情面に訴える美を生み出す能力、人を納得させる話のできる能力、一見ばらばらな概念を組み合わせて何か新しい構想や概念を生み出す能力などだ。
ハイ・タッチとは、他人と共感する能力、人間関係の機微を感じ取る能力、自らに喜びを見出し、また、他の人々が喜びを見つける手助けをする能力、そしてごく日常的な出来事についてもその目的や意義を追求する能力などである。
この6つの感性(センス)があなたの道をひらく。
1.機能だけでなく「デザイン」
2.議論よりは「物語」
3.個別よりも「全体の調和(シンフォニー)」
4.論理ではなく「共感」
5.まじめだけではなく「遊び心」
5.モノよりも「生きがい」
これら6つの感性は、ますます私たちの生活を左右し、世の中を形作っていくようになる。
2. 感想
論理だけでは足りない時代に、「感性」が求められる理由
- ダニエル・ピンクは本書で、これからの時代を生き抜くために必要なのは、左脳的な論理や分析だけではなく、右脳的な創造性と感性であると語ります。これは単なるクリエイティブ職に限った話ではなく、ビジネスパーソンすべてに向けられたメッセージです。なぜなら、従来「高度な知的労働」とされてきた業務の多くが、
・IT化(=コンピューターに代替)
・グローバル化(=海外アウトソース)
によって、これまで私たちが担ってきた領域から外れつつあると主張しています。 - だからこそ、「あなたにしかできない仕事って何だろう?」という問いには、ただ仕事の役割を果たすだけでなく、そこに“意味”を生み出せる存在であることが、これからの時代に必要なのだと本書は語っています。
「ハイ・コンセプト」と「ハイ・タッチ」—右脳で考え、右脳でつなぐ
- ピンクはこれからの人間に求められる能力を、「ハイ・コンセプト」と「ハイ・タッチ」という2つの視点で語ります。
• ハイ・コンセプト
・ばらばらな情報を統合し、新しい価値を生み出す能力
・論理ではなく直感で全体を捉え、アイデアを組み合わせるセンス
・ストーリーテリングやデザイン思考、クリエイティブな発想
• ハイ・タッチ
・共感力、心の機微を捉える力、人との信頼関係を築く力
・遊び心やユーモア、喜びを生み出す感受性
・人生の目的や生きがいを感じ取るセンス - この2つの感性は、情報があふれる今の時代において、「自分たちらしい判断」を下すために欠かせない力です。特に日本のビジネスの現場では、これまで軽視されがちだった「感性」や「共感」こそが、これからの主役になる。そんな強いメッセージが本書には込められています。
「6つの感性」が未来をひらく羅針盤になる
- ピンクは、「右脳的知性」を象徴する6つの感性(センス)を提案しています。
1. 機能ではなく「デザイン」
→ どう便利かだけでなく、どう美しく、心地よいか。
2. 議論ではなく「物語」
→ データや主張より、人の心に残るのはストーリー。
3. 個別ではなく「全体の調和(シンフォニー)」
→ パーツで見るのではなく、全体のつながりで捉える。
4. 論理ではなく「共感」
→ 相手の立場で感じ、考え、伝える力。
5. まじめだけでなく「遊び心」
→ 楽しさや創造性が、人を動かす源になる。
6. モノではなく「生きがい」
→ 物質的な豊かさより、意味ある人生の探究へ。 - これらはどれも、AIやロボットには真似できない、人間にしかない力です。そしてこの6つのセンスは、単なる感覚ではなく「磨くことができる能力」であるというのが本書の提案です。
3. この言葉の活かし方
「論理+感性」の統合で、仕事の質を高める
具体的な活かし方
• プレゼンでは数字や機能だけでなく、使う人の感情に響く話を織り込む
• チームミーティングでは、成果だけでなく「感じたこと」や「学んだこと」を共有する時間をつくる
実践例
提案資料にスペック比較表を載せるだけでなく、「この製品を使うことで、どんな体験ができるか?」というストーリーを図解で示す。顧客の共感が高まり、提案の納得度が大きく向上する。
「6つの感性」で自分の仕事を見直す
具体的な活かし方
• メールや報告書に、“事実”だけでなく“背景や意図”を含む物語性を持たせる(物語)
• 役割や専門にとらわれず、全体を見渡して関係性を考える(シンフォニー)
• 顧客へのインタビューなどで「相手の感情」に注目してみる(共感)
• かたい話ばかりではなく、雑談の中にクスッと笑える遊び心を忍ばせてみる(遊び心)
• 働く意味・やりがい・社会的な意義を問い直す(生きがい)
実践例
サービス改善ミーティングで「何が不便か」だけでなく「お客様はこのサービスを使って、どんな気持ちになっているのか?」を話題にすることで、“問題解決”から“体験設計”へと議論の質が変わる。
「右脳を使う時間」を意識的に設ける
具体的な活かし方
• 書く、話す、考えるときに、「感情」や「直感」を1つ添える
• 意識的に「意味」「つながり」「雰囲気」に注意を向けてみる
実践例
企画を練る前に、「なぜこのテーマをやるのか?」をA4紙1枚に「言葉」ではなく「絵」や「図」で描き出す。構造や要点のつながりが見えやすくなり、新しいアイデアが浮かびやすくなる。
4.まとめ
本書が伝える「ハイ・コンセプト」と「ハイ・タッチ」、そして「6つの感性」は、スキルの話にとどまらず、これからの時代をどう生きるか、人としての“あり方”に深く関わる提案です。
• AIやロボットではなく、“人間だからこそできる仕事”をすることが生き残りの鍵
• 6つの感性はすべて、訓練し、磨き、実践することができるスキルである
論理と感性、数字と物語、成果と意味。どちらかではなく「どちらも使いこなす人」こそ、次の時代をつくる存在になるでしょう。
あなたの仕事や人生には、いまどんな“右脳の余白”があるでしょうか?
今日から少しだけ、「デザイン」「物語」「共感」に目を向けてみてください。そこに、これからのあなたらしい価値創造のヒントが隠されているはずです。
5.「私の読書メモ」でご紹介した本

ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代 (Amazon)
カテゴリー
・私の読書メモ
Copyright Ooba Consulting Office All Right Reserved.
本コンテンツをを無断複製することや転載することを禁止します