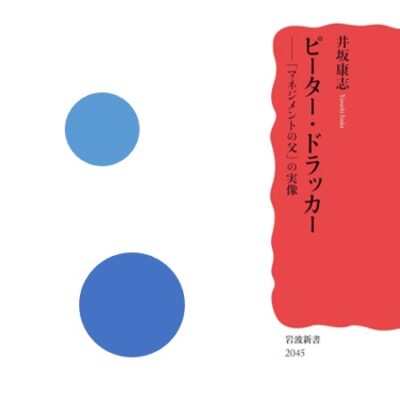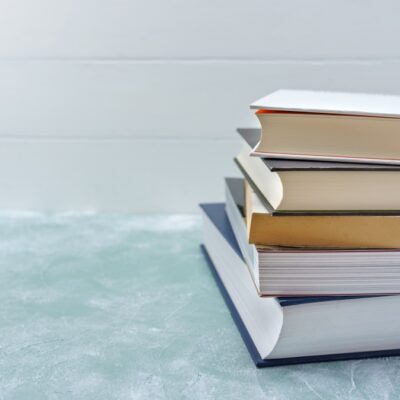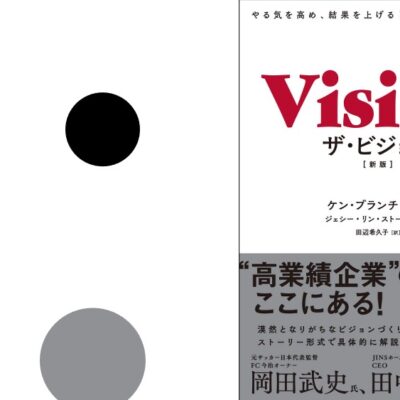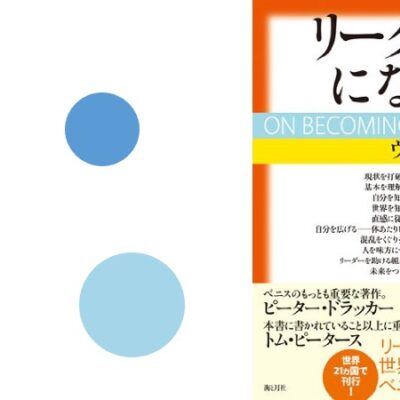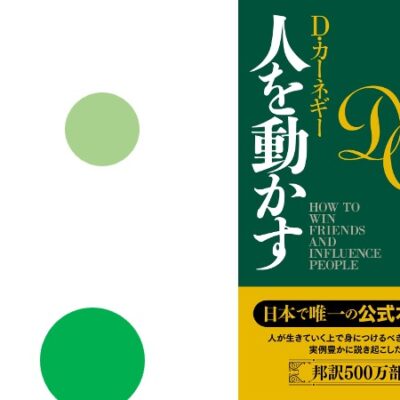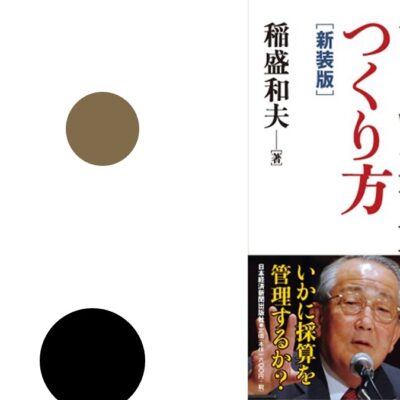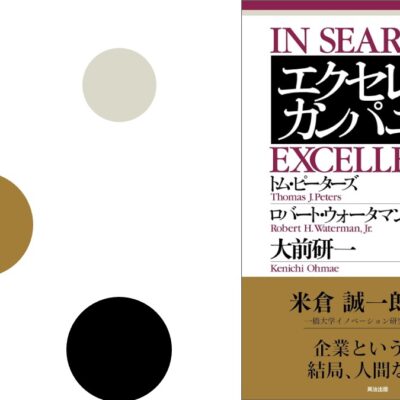松下幸之助「商売心得帖」 私の読書メモを紹介します。
著者:松下幸之助
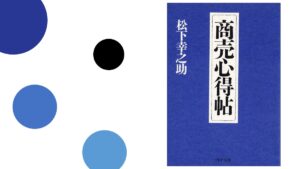
目次
• 1.本書からピックアップ
• 2.感想
• 3.この言葉の活かし方
• 4.まとめ
• 5.私の読書メモで紹介した本
1.本書からピックアップ
日々の商売を力強く進めていくために、大事なことの1つは、いわゆる世間と言うものを信頼することだと思います。ありがたいことに、世の中と言うものは、こちらが間違ったこと、検討はずれのことをやらない限り、必ず受け入れ、指示してくださるものだと言えましょう。つまり、正しい仕事をしておれば悩みは起こらない。悩みがあれば自分のやり方を変えれば良い。世間の見方が正しいのだ。だからこの正しい世間と共に懸命に仕事をしていこうと考えているわけです。
いかなる商品であっても、私の店のものは私の方で値段を適当に決めるのだ。それは安売りをしているところよりも高いと言う場合もある。その高いと言う場合には、自分の魂料が入っている。店の信用保証料が入っている。だから、何かの時に私のほうは責任を持ちますよ、と言うことを、堂々と主張できるような商売でなくてはならないということです。
商売をするには、自分の扱う商品を充分吟味し、自信を持って販売することが大事である事は言うまでもないでしょう。ただその際の心がけとして、お得意先の仕入れ係になったつもりで、これを吟味することが大事だと思います。自分はお得意先の仕入れ係だと考えれば、お得意先は今何を必要とされているか、どういう程度のものをどれほど欲しておられるのかと言うことを察知しつつ、そういう目で商品を吟味してお得意様の意にかなうようにお勧めしなければなりません。
2. 感想
「世間を信頼する」ことが商いの根本
- 松下幸之助が語る「世間を信頼する」という言葉には、商売における“お客様との信頼関係”を根本に据える哲学が表れています。現代では「マーケット」や「顧客インサイト」と言い換えられるこの“世間”という存在を、松下氏は「正しい判断をする存在」として尊重し、信じています。
- つまり、「商売で悩みが生まれるのは、世間ではなく、自分のやり方に問題がある」と考え、常に自らの姿勢を見直すという謙虚な姿勢が強く印象に残ります。これは、現在のビジネスでいう「顧客志向」「フィードバックループ」「ユーザーセントリック」の先駆け的な思想といえるでしょう。
- また、「正しい仕事をしていれば、世間は必ず受け入れてくれる」という信念は、誠実な商いの積み重ねがブランドとなり、信用となるという普遍的な真理を伝えています。
「値段に魂を込める」ことの意味
- 松下氏は価格について、小売店の方と話をする中で「自分の魂料が入っている」「店の信用保証料が入っている」と相手が気づきを得たと述べています。この一節は、単なる価格設定の話ではなく、自分が売るものにどれだけ誇りと責任を込められるかという、商人としての姿勢のことです。
- 現代ビジネスにおいては、競争力=価格の安さという誤解がはびこりがちですが、この言葉は、価格には「価値」と「信頼」が反映されるべきであるというメッセージを私たちに投げかけています。
- 「高いものを売るな、安く売るな、納得して売れ」という信条にも通じるこの考えは、まさに “価格ではなく価値で勝負する”ビジネスの原点を再認識させてくれます。
「仕入れ係の視点」で商品を選ぶ—究極の顧客視点
- 商人としての矜持は、自社の商品への自信とこだわりに表れる。しかし、それ以上に大切なのが「お客様の立場に立つ」ことだと松下氏は説きます。
- 「自分はお得意先の仕入れ係だと考えよ」という言葉には、“売る”ではなく“役に立つ”という商売の本質が込められています。これは、現代マーケティングで言う「カスタマージャーニーの理解」や「共感ベースの提案営業」そのものであり、お客様のニーズを先回りして想像し、寄り添い、最適な提案をするという “奉仕の精神”をビジネスに持ち込むことの重要性 を教えてくれます。
3. この言葉の活かし方
顧客の声を「正」として受け止め、姿勢を見直す習慣をつくる
具体的な活かし方
• アンケートやレビュー、面談で得た意見を定期的に社内で共有・改善につなげる
• 結果が出ないとき、「世間が悪い」のではなく「自分たちのやり方に問題がないか」を問い直す文化をつくる
実践例
営業活動で成約率が落ちてきたとき、値下げをするのではなく、「顧客は今、何に悩み、何に共感するのか?」という視点で、商品説明・提案資料を見直す。
商品やサービスに“魂料”を込め、価格に責任と自信を持つ
具体的な活かし方
• 安売りをする前に、「自分たちのサービスや対応が価格に見合っているか」を見直す
• 値段に対して「保証できる何か」があるかどうかを問い直す習慣を持つ
実践例
コンサルティングサービスの料金設定で、単に「時間単価」で計算するのではなく、「成果に対する責任」「情報の質」「対応力」「信頼関係構築にかかる労力」など、無形の価値を含めて正当な価格設定を行い、納得して提案する。
「顧客の仕入れ係」として、顧客のニーズに寄り添う提案を行う
具体的な活かし方
• 提案内容を決める際、相手の立場になりきって「今、何を選ぶか?」を考える
• セールスや商談の場では、相手の「選択の安心感」をつくることを第一に考える
実践例
BtoB営業で、スペックの良さをアピールするのではなく、相手の現場課題・上司への説明・コスト負担・運用負荷といった「相手側の判断基準」を意識しながら提案内容を設計し、「選びやすさ」と「安心」を提供する。
4.まとめ
本書が示す商売の心得は、単なるテクニックではなく、商いに向き合う“心の姿勢”を磨く道しるべです。松下幸之助が遺した言葉は、いまなお経営や営業の現場で生き続ける本質的な考え方を伝えています。
• 値段は単なる数字ではなく、誠実さと信頼の証である
• 顧客の立場に立ち、役に立つ提案をすることこそ、商売人の使命である
松下氏の教えを日々の商いに取り入れることで、信頼される個人・組織・ブランドが育まれていくはずです。あなたが今取り扱っている商品・サービスにも「魂料」は込められているでしょうか?今日から、商売の原点に立ち返り、お客様の信頼を積み重ねていく一歩を踏み出してみてください。
5.「私の読書メモ」でご紹介した本

松下幸之助「商売心得帖」 (Amazon)
カテゴリー
・私の読書メモ
Copyright Ooba Consulting Office All Right Reserved.
本コンテンツをを無断複製することや転載することを禁止します